自分ならどんな中小企業でも、たちまち儲けさせてみせる。
経営には勝方程式があると言う


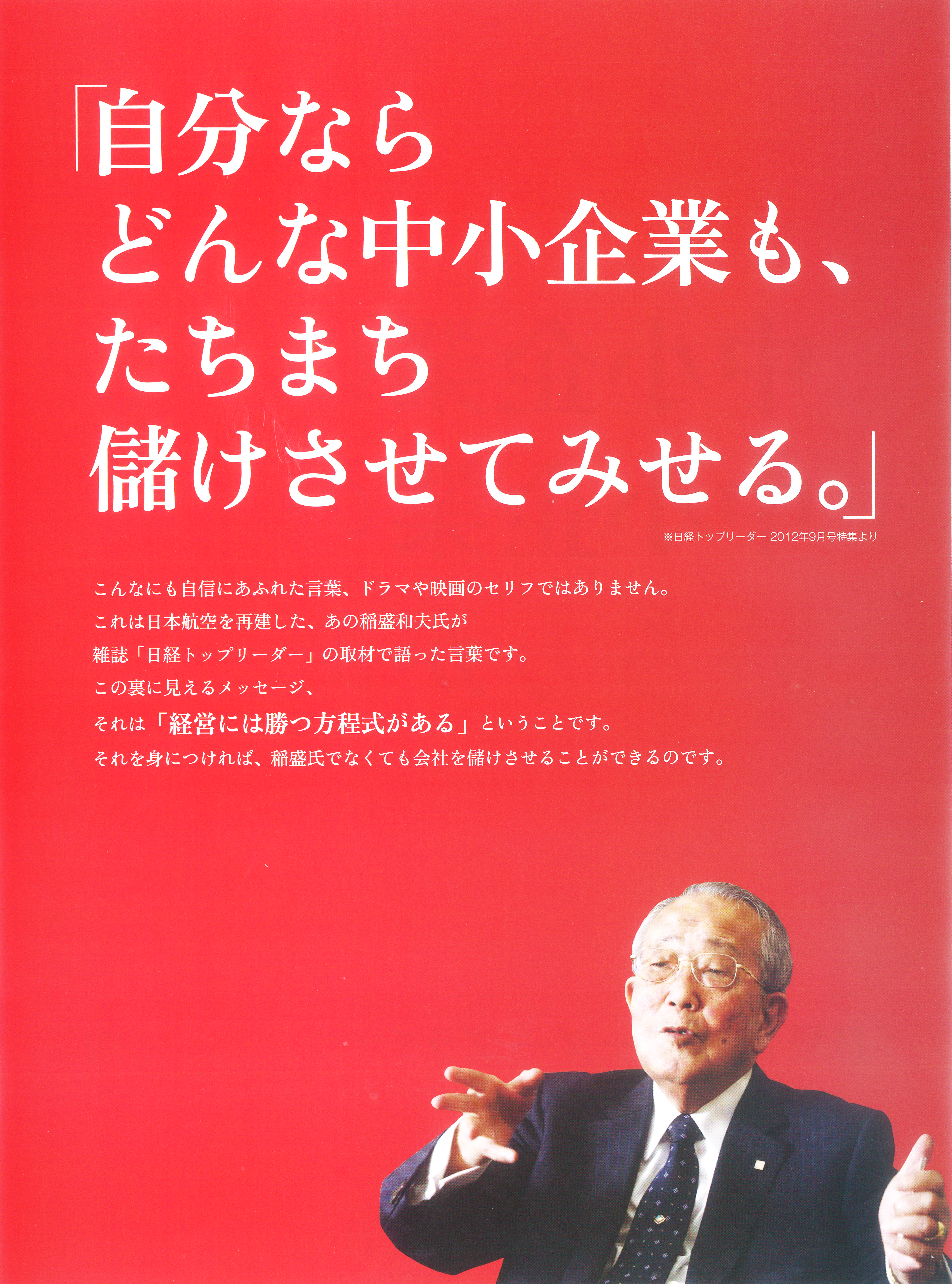
1、本をたくさん読んだ
2、よく考えよく行動した
3、アメーバ―経営を考案した
稲盛経営12ヵ条
1. 事業の目的、意義を明確にする
公明正大で大義名分のある高い目的を立てる。
2. 具体的な目標を立てる
立てた目標は常に社員と共有する。
3. 強烈な願望を心に抱く
潜在意識に透徹するほどの強く持続した願望を持つこと。
4. 誰にも負けない努力をする
地味な仕事を一歩一歩堅実に、弛まぬ努力を続ける。
5. 売上を最大限に伸ばし、経費を最小限に抑える
入るを量って、出ずるを制する。利益を追うのではない。利益は後からついてくる。
6. 値決めは経営
値決めはトップの仕事。お客様も喜び、自分も儲かるポイントは一点である。
7. 経営は強い意志で決まる
経営には岩をもうがつ強い意志が必要。
8. 燃える闘魂
経営にはいかなる格闘技にもまさる激しい闘争心が必要。
9. 勇気をもって事に当たる
卑怯な振る舞いがあってはならない。
10. 常に創造的な仕事をする
今日よりは明日、明日よりは明後日と、常に改良改善を絶え間なく続ける。創意工夫を重ねる。
11. 思いやりの心で誠実に
商いには相手がある。相手を含めて、ハッピーであること。皆が喜ぶこと。
12. 常に明るく前向きに、夢と希望を抱いて素直な心で
これ、実行してますね。
稲盛和夫 JAL奇跡の復活 過去最高益へ
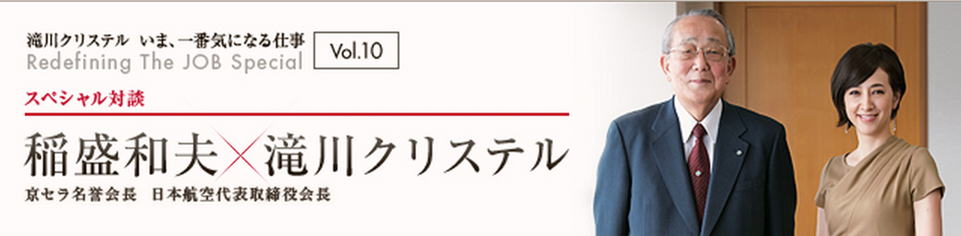
2010年1月に日本航空の代表取締役会長として日航再建をタダで引き受けた。
日経電子版より
稲盛
「何も知らない稲盛が会長を務めたって必ず2次破綻するだろう」
「晩節を汚すのは目に見えている」とか、いろいろなことを言われました。着任してみますと、
やはり日本航空の中に“真のリーダーがいない”ということがはっきりわかりました。
すべてが悪い意味での官僚組織になっていたのです。
現場で叩き上げて必死に生きてきた人ではなく、
一流大学を出てエリートコースを歩いてきた人が全体を支配していたんですね。
すぐ「これは大変だ」とわかったので、まずは幹部社員の意識改革に着手をしたんです。
昨年の6月に17回、夜仕事が終わってから幹部50~60人を会議室に集めて、
「人間としてどうあるべきか、集団のリーダーとしてどうあるべきか」という議論を繰り返しました。
滝川
稲盛さんの意識改革の意図は、すぐに皆さんに理解してもらえましたか?
稲盛
やはり最初はかなり違和感があったようです。
しかし、意識改革なくして再建はあり得ないと思ったので必死になってやりました。
例えば夜9時くらいになると、無給の私がビールを買って差し入れる。
そうやって一杯飲みながら話すとちょっと心を開きますから、
いろいろと反論を言い始める。言わせておいて、「そりゃあんた、おかしいよ。
その意識では八百屋も経営できないよ」などと話す。
そういう対話を続けるうちに、社員全体の意識がみるみる変わっていきました。
もともとは暴れん坊で反発も一番強かった人がコロッと変わってくれると、
後は将棋倒しみたいに変わっていった。
「もっと早く会長の話を聞いていれば、私の人生も変わったと思います。
JALもここまでならなかったと思います」と言ってくれる人が出てきた。
そして、意識が変わっていくにつれて、業績も上がっていきました。
滝川
そんな風に、一度は再建不可能といわれるところまで陥った日本航空の業績をも変えてしまった。
稲盛さんの意識改革の柱になっているものとは、ひと言で言えばどういうものなのでしょうか?
稲盛 私のフィロソフィ(=哲学)というのは、人間として最低限持つべきベーシックな道徳観なんです。
実は、今まで日本のエリートたちはそういう道徳観、倫理観というものをないがしろにしてきた。
なぜ20年近い間、日本経済全体がこれほど低迷したかというと、
日本の各階層のリーダーに、その基本的な哲学が欠けていたからです。
もっと言えば、哲学に基づく高い目標や強い願望、意志でそれを実行していこうという“心の強さ”が欠けていたことが一番の要因です。
かつて世界中から奇跡といわれた戦後の復興を果たした時、日本の産業界は強かったし、実は今でも強いんです。
ものづくりの技術、人材、資産の面においても、今でも世界で屈指の力を持っている。
それにも関わらず、日本の後を追いかけてきた韓国のサムスン電子やLG電子、現代自動車の後塵を拝してしまった。
しかしリーダーたちには、追い抜かれた新興国に、再び追いついていこうという気力もない。それが問題なんですね。
滝川
しかし一方で、被災地の方々の“強い精神力”は、今回、本当に世界中の人々から称賛を集めました。
稲盛
今回の震災で日本人が見せたビヘイビア(=振る舞い)は本当に素晴らしいものでした。
幕末の開国時、日本は農業国家で近代産業もなかったのに、
諸外国の方々は日本の田舎を歩いて非常に感動したそうです。
小ざっぱりした質素な木綿の着物で、贅沢なところはないけれども、
道行く人に笑顔で挨拶を欠かさない。
そんな姿を見て「心が洗われるようだ。
日本という国は素晴らしい」と絶賛したという記録が残っています。
そんな“日本人の心根”は経済大国になった後も、消えていなかった。それを知って非常に誇りに思いました。
ただ、今回のような日本国全体の危急存亡の時には、スマートで上品なだけでは駄目です。
「何くそ!」という野人のごときバイタリティや強さも必要だと思います。
滝川
礼節の心と野人のようなバイタリティ――。
それは、本業に努めながらも、ここ30年弱の間、「盛和塾」で中小零細企業のリーダーを精力的に育成されてきたこと。
そして現在、中国、ブラジル、アメリカでもその礎を築いている稲盛さんご自身の経営者哲学でもある気がします。
そこでもう少し、今この危機において必要とされる「真のリーダーの条件」をお聞かせください。
稲盛
私は今、会長として、日本航空の再建に没頭しています。その中でも感じるのですが、
リーダーというのは、中小企業であれ大企業であれ、中央政府であれ地方自治体であれ、
本来、無生物である組織に対して“命を吹き込む”のが役割だということです。
リーダーが持っている人間性や思いを組織に浸透させ、組織を動かしていかなければならない。
その時に一番大事なことは、己を捨てることです。
リーダーが利己的な自分というのを少しでも持つと、組織を間違った方向に動かしていく。
だから、フェアで公明正大でありながら、全身全霊で組織に命を吹き込まなければならない。それは平時においても必要です。
そうすれば、「いざ鎌倉」という時にもひとつの方向に向かって組織が団結できます。
例えば私が日本航空の会長になって、昨年の4月から3月までの第1期は売上1兆4000億弱、
営業利益1900億弱を計上できる見込みです。
しかし、そこへ来ての3月11日の大震災です。
海外からのお客様もぱったり来なくなり、国内も4月にはまた赤字転落です。
しかし、私はこれを「慢心してはならん」と神様が与えたもうた試練だと思うことにしました。
それを真正面から受け止めて、第2期も素晴らしい業績で終えるために、今、必死で頑張っています。
滝川
有難うございます。
では最後に稲盛さんの仕事観と読者への提言をお願いします。
稲盛 私は仕事というのは自分自身の心を立派にしていくためのものだと思っています。
それはどんな仕事においても同じです。
今回、私たちは大地震に見舞われましたが、世の中というのは非常にフェアなものであって、
未来への希望を持ち、不平不満をもらすことなく、美しい気高い心で、
一生懸命努力をする人には必ず素晴らしい未来が開ける。
だから我々はまず、自分と日本には必ず素晴らしい未来があると信じなければいけません。
時代を動かすのも、経済を動かしていくのも、
あらゆるものの原動力というのは人間の“心の状態”で決まるからです。
「何とかしなきゃならん」という強い意志を持って、何をも恐れず必死で実行していく。
ひとりのリーダーに頼ることなく、全国民が奮起して、
「眠っていた日本人魂に火がついた」と言われるようなことをやってのける、
そうすれば日本は必ず、以前にも増して素晴らしい国になれると私は確信しています。
ある、インタビュー
―小さい頃の稲盛名誉会長は、どのような少年でしたか。
両親の話では、子供の頃の私は明るく活発で、
親戚などが集まる場ではみんなを笑わせたりするような子供だったようです。
そのいっぽうで、近所でも有名な甘ったれの泣き虫で、
一度泣き出したらなかなか止まず、「三時間泣き」とあだ名されるほどでした。
そのように根が内弁慶で臆病なものですから、小学校に入学しても、
最初の頃は母親がついてきてくれなければ学校にも行けませんでした。
それでも、何年か経つ内に学校の生活にも慣れ、だんだんガキ大将ぶりを発揮するようになりました。
せいぜい中派閥のボス程度でしたが、当時の私にとっては、
成績の良し悪しよりも、どうやってグループを掌握するかが最大の関心事だったのです。
卑怯なところを見せればすぐに子分たちから見放されてしまいますから、
負けると分かっている喧嘩もしなければなりません。
また、ただ腕っ節が強いだけでもだめで、おやつを配ったりといろいろ気遣いも要ります。
思えば、この頃から、遊びを通じて、集団を率いるためにはどうあらねばならないかを、
少しずつ学んでいたような気がします。
ある、投稿記事
幼い頃はガキ大将だったため、内申点を悪く付けられ、そのせいか、
名門校・鹿児島第一中学の受験に失敗、しかも結核にかかるという不運に見舞われます。
終戦後、「生計を支えるために働け」という親の反対を押し切って高校に進み、卒業後、大阪大学医学部を受験しますが、不合格。
併願した鹿児島大学工学部に進み、有機化学を専攻します。
就職は専門を活かそうと帝国石油を志望しますが、これも失敗します。
その後、指導教授の紹介で無機化学の技術者として終戦から10年後の1955年に松風工業に入社します。
当時、無機化学は人気のない分野で、稲森は卒業前の半年で有機から無機に転向し、卒業論文を書いたといいます。
稲森の就職した松風工業は明治以来の送電線用のガイシメーカーでしたが、戦後の混乱で技術は遅れ、
業績は低迷していました。稲森は入社後、特殊磁器(ファインセラミックス)の研究に携わりますが、
会社は業績悪化から銀行の管理下にあり、労働争議は激しく、給料の支払も遅れがちという状況でした。
稲森が住むことになった会社の寮も、今にも倒れそうなオンボロの建物で、会社周辺の店に行くと
「あんな所で働いていると嫁も来ないぞ」と笑われる有様でした。
こうした状況に失望し、仲間と一緒に退社して自衛隊へ入隊することも考えたと言います。
そして彼は転職に必要となる戸籍謄本を実家に送れと頼みますが、稲森の兄が「入社半年で会社を辞めるとは何事か」と怒り、
その手紙を握りつぶしたと言います。
この出来事の後、稲森は考えを変え、技術者としての研究に没頭します。
組合員からの嫌がらせに耐える研究に打ち込んだ稲森は当時普及し始めていたテレビのブラウン管に使われる部品を高周波絶縁用の弱電用磁器を使って製造する技術に取り組みます。
そして1956年、マイクロ・クリスタリン・ワックスを使った部品(U字ケルシマ)の開発に成功します。
これは画期的な部品で、松風工業は松下電子からの注文に応じ、量産化に入り、1957年には同社の売上の12%を占めるようになります。
しかし、社内は労使が対立、組合はストライキに入る状況でした。 だが、稲森が属する特磁課はストライキの最中も泊まりこみで生産を続けます。
何よりも納入先の信用を大切にしたものでした。
このため、組合員からは嫌がらせを受け、「会社のイヌ」「ええカッコするな」などの罵声を浴びせられます。
しかし、稲森はひるむことなく工場に食料を持ち込み生産を続けます。
完成した部品は女子従業員が納品のため、こっそりと工場から持ち出します。
この女子従業員が実は後に稲森の妻となります。
稲森の開発したテレビのブラウン管用の部品は好調でしたが、松風工業全体としての業績は好転しません。
1958年、稲森が主任に昇進してから3カ月後、日立製作所から松風工業にオールセラミックスの真空管を作って欲しいという要望が寄せられます。
稲森が担当しますが、満足の行く性能が得られません。
経営陣の督促が続くなか、稲森の上司の技術部長は稲森の経歴や能力を侮辱します。
これに対して、日頃、不満のあった稲森は即座に辞表を提出します。
「65才になるのを機に閑職に退き、仏門に入る」
と宣言して話題を呼んだ稲盛和夫。
年間売上一兆七〇〇〇億円の企業グループを率
いる稲盛は、平成九年六月の株主総会で 「京セ
ラ」「第二電電(DDI)」の、いずれも名誉会長
となり、京都の臨済宗門福寺で得度するという。
27才で「京都セラミック」(当時)を設立し、
強烈なカリスマ性で〝日本経済界の寵児″とまで
称されるようになった稲盛の、その伝説を彩るエ
ピソードの数々は凄まじいの一言。
創業の頃は、部下への質問は容赦がなく、会議
の席では泣き出す幹部も出るほど、問題点を徹底
して追及される。当然、ついていけない者もいる。
「京セラの退職者は非常に多い。『三分の二は五年
以内に辞める』ともいわれる。(中略)心が通じ
合えない者は辞めて結構。これが稲盛の姿勢だ。
その代わり、筋金入りの京セラマンは忠誠心、
情熱ともに桁外れで、休日出勤、深夜残業はもち
ろん、注文をとるためなら土下座も厭わず。「お
客様のために召し使いとなってサービスに徹す
る」と張り切る営業マンは数知れず。社内でも怒
鳴りあったり、涙を流しながら主張しあったりと、
そのテンションの高さは他に例をみない。
そして、京セラ社員の団結心は死んだ後も続く。
先の『血気と深慮の経営』にこんな記述がある。
「京都府八幡市八幡の洞ヶ峠の目と鼻の先に、臨
済宗妙心寺派の円福寺がある。鬱蒼とした三万坪
の広さ。そこに京セラ従業員の墓がある。五四年
に京セラ創立20周年の記念行事の一つとして建
てられたものである。京セラ発展のために死力を
尽くして倒れた社員や、創立に力のあった方々の
名が、慰霊室の銘盤に刻まれている。〝死して後
までもパートナーとして一緒にいてほしい。
いかにも稲盛らしい願いである」
さながら稲盛教の教祖、といった趣だが、この
鬼気迫るパワーを持った集団を率いる稲盛の半生
を振り返ると、貧困と病気、そして度重なる挫折
のなかで、強靭な精神力をただ一つの武器として、
生きてきたことが分かる。
稲盛和夫は昭和七年一月、鹿児島市内の小さな
印刷業者の次男に生まれた。きょうだいは七人。
尋常小学校高等科一年で終戦を迎えるが、鹿児島
の街全体が激しい空襲に晒され、和夫少年の自宅
店舗も焼失。一家は貧乏のどん底に突き落とされ
た。しかもこの年、結核に冒され、死線をさまよ
う恐怖も味わっている。絶望感を募らせるしかな
かった少年時代、近所の主婦の勧めで「生長の
家」の創始者、谷口雅春の『生命の実相』を読ん
だのが、宗教や哲学に関心を持つきっかけになっ
た。
志望した中学の受験には2度失敗。大学も第一
志望の大阪大学医学部をこれまた失敗、地元の鹿
児島大学工学部に進み、応用化学を専攻する。優
秀な成績で卒業するが、有力企業は地方大学に冷
たかった時代。東京の大手石油会社をはじめ、こ
とごとく振られる。「頭がよくって、腕っぷしも
強いインテリヤクザにでもなろうかIと鹿児島
市内の天文館通りにある〝小桜組″の事務所の前
を、稲盛青年はとつおいつ往復したものであった」
自暴自棄になった和夫を救ったのが、大学の担
当教授だった。「松風工業」という京都の高圧線
碍子メーカーに推薦してくれたのである。ところ
がここが首が回らぬほどの赤字会社で、給料も遅
配の連続。注目され始めたばかりのセラミックス
の開発要員として採用された和夫は、それでも仕
事に没頭し、テレビのブラウン管用の部品開発に
成功、頭角を現す。
だが、三年後、技術開発の進め方をめぐって上
司と衝突し、退職してしまう。昭和33年秋のこ
とだ。翌34年4月、同じく会社を辞めた7人の
「同志」と共に会社を設立、これがファイン・セ
ラミックの専門メーカー「京都セラミック」(昭
和57年、京セラに社名変更)だった。この時、
志を確かめるべく、稲盛の提案で血判状をしたた
めたエピソードは今でも語り草になっている。
知人からの出資を募って、会社をスタートさせ
た稲盛は、「とにかく食わねばならない」と、部下
を猛烈に叱りとはしながら働いた。ところが一
年後、思わぬ事態が勃発する。地元高校から入社
した同期二人が、これも血判状をつくって待遇
改善と将来の保障を要求して直談判に及んだのだ。
しかし、28才の稲盛は「自分の親、兄弟の面倒
も見れんのに、将来の保障なんかできるか」と突
っぱねた。交渉は三日三晩続き、次々に説得に屈
したが、最後の一人は退社を覚悟して抵抗する。
その時の稲盛の言葉が凄まじいというか、大時代
的というか、常人にはとても吐けないものだった。
日く「おれは命を賭けてでもこの会社を守ってい
くつもりだ。裏切られたと思ったら、ドスてこの
おれを刺し殺してもいい」
かくして、〝反乱軍″は全員投降した。当時は
「あまりの猛烈経営ぶりに、しばらくは中途退職
者があとを遜たないほどだった。世間は、『狂徒
セラミック』『狂セラ』などと陰口を叩いた」
という。
だが、稲盛の強烈な個性だけが京セラの強みではない。
現在、IC(集積回路)パッケージは間違いなく
世界のナンバーワンだし、マルチレイヤーパッケ
ージの技術もIBM等と並んでトップクラス。アメリカ
への進出も比較的早く、創業6年目の昭和
40年にはテキサス・インスツルメンツから受注、
京セラ製晶が間接的ながらアポロ計画の電子機器
に使われている。翌41年にはIBMからのセラ
ミックパッケージの大量受注も実現、一躍、国際
企業として名を馳せた。
昭和59年には稲盛財団を設立し、世界の研究
者を対象に国際賞「京都賞」を設けている。この
賞は「民間人が作った純学術的な国際賞としては
最高のもの」と言われ、日本よりむしろ欧米で評
価が高い。
また同年、ソ土-、ウシオ電機、セコムなどに
呼びかけて第二電電企画(現・第二電電)を誕生
させ、自由化を控えていた電気通信事業に参入。
巨人NTTに真っ向からケンカを売り「無謀な挑
戦」と散々書き立てられたが、現在、従業員二八
○○名、年間売上約五五〇〇億円に達している。
稲盛は参入した当時を振り返って「毎晩〝動議尊善
なりや、私心なかりしか″と呟きながら寝ており
ました。そういう行みたいなことをやっているう
ちにどんどんやれそうな…まあ、見えてくる、と
いうんですか。踏み切るときはもう迷わなかった
ですね。成功に対する確信がありました」と、
先端企業のトップらしからぬ、なにか宗教家にも
似た、深遠な言い回しで語っている。
現在、稲盛はアメリカのモトローラ社が提唱す
るイリジウム (衛星携帯電話事業)構想を推進中
だが、計画によれば平成10年半ばには携帯電話
で地球上どこでも電話をかけられるシステムが完
成するという。出家とテクノロジー。一見すると
両極端とも思えるこの二つが、稲盛のなかでは何
の矛盾もなく同化していることになる。「稲盛フ
ィロソフィー」と言われる所以である。